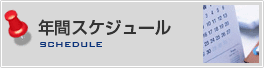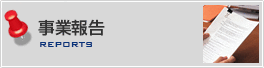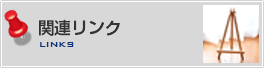山形支部
山形支部 の記事一覧
2023年 山形支部
2024年01月17日(水曜日)
76回示現会山形展は6月28日から7月2日までの会期で山形美術館において開催された。
前日には本部より錦織重治常務理事をお迎えし、展示から作品の公表など懇切丁寧なご指導とご助言をいただいた。
あわせて開幕日には一般観客向けのギャラリートークをお願いし、ユーモアのある解説に納得し和やかな時間を持つ事ができた。
収まりつつあるコロナ禍の中、公募作品を含め、90点余が会場をうめつくした。悪天候にもかかわらず入場者も昨年をわずかに上回り、今後の励みとしたい。
例年、同時開催していた小品展を今年は11月に予定している。その他、5月には、真室川で写生会を開催。残雪の残る鳥海山を望み筆を走らせた。
8月には猛暑の中、県展むけの研究会を実施する。
2022年 山形支部
2023年02月20日(月曜日)
この度75周年記念示現会山形展を6月29日から7月3日までの会期で山形美術館において開催した。
前日には本部より佐藤祐治常務理事をお迎えし、展示から作品の講評など懇切丁寧なご指導とご助言をいただいた。あわせて開幕日には一般観客向けのギャラリートークをお願いし、既知に富んだ作品の解説に会場が大いにもり上がった。
長引くコロナ拡大での中、公募作品を含め97点が会場を埋めつくし入場者も昨年を上回り100人増となった。これは会員の今後の活動の励みとなる一歩であろう。ただ会場の都合で同時開催していた小品展が実施できなかったことは残念であった。
その他。5月には、庄内浜で写生会を開催、真っ赤な夕日に感激。また8月の猛暑の中、健展向けの研究会を実施した。
2021年 山形支部
2022年01月17日(月曜日)
支部事業の中心になる山形展は6月29日から7月4日までの会期で山形美術館において開催された。
前日には本部より成田理事長をお迎えし、展示から作品の講評など懇切丁寧なご指導ご助言をいただいた。2年ぶりのコロナ禍での開催に不安もあったが、公募作品を含め96点が会場をうめつくし、入場者も例年の7%減となったものの連日の盛況に安堵した。同時開催として彩画堂ギャラリーでの小品展も実施した。山形では中央展の巡回展は他に例がなくこの開催は芸術文化の向上に大きく貢献しているものと思う。また今年は支部70回記念展にあたり記念画集も発刊し、理事、支部長各位にも謹呈したところです。
その他、8月には県展向けの研究会を実施、10月には蔵王山麓で写生大会を予定している。
2020年 山形支部
2021年03月30日(火曜日)
今年の梅雨明けは例年より遅く8月にずれ込んだ。その直前、本県は大雨災害に見舞われ、最上川とその支流が氾濫した、「羽越災害」以来53年ぶりのことだ。
私の住む村山市もその中央部を貫流していることから百世帯が浸水した。中でも大淀地区は最上川の大蛇行部にあたり、県内外の写真家や画家が訪れる風光明媚な地区として知られているが、川岸にあるアトリエ3棟も床上浸水を被った。幸い高台にたつ最上川美術館は無事だったが。稲作、舟運、文化等の発展に恩恵を与えてきた、まさに山形県の「母なる河」。一旦牙をむくと人力では制御できないという自然の恐ろしさを改めて知らされた。
展覧会開催については、新型コロナ感染対策にともない本県もほとんど中止になったが、唯一令和元年に中央展に出品した作品を対象にした「中央展出品選抜絵画展」が山形市で開催された。3月中旬から7月末まで(途中休みあり)の期間で20団体、73展出品中、示現会関係が最も多く16点の出品であった。他団体の中央展出品作と一緒に陳列する形の珍しい企画の展覧会は私達にとっても有意義なものとなった。
最後に山形支部も秋に向け活動を始めようとしている。今の閉鎖的な状況を打ち破るため避暑も兼ねながら9月10日に蔵王山麓での写生会を企画した。広々とした自然の中、久しぶりに仲間と顔を合わせたい思いでいっぱいだ。
2019年 山形支部
2020年01月07日(火曜日)
山形巡回展は、例年、7月中旬に山形美術館で開催しています。恒例化に伴い、50数名を数えていた会員がここ数年で33名まで減少し、展示や撤去など労力面での負担が大変になって来ているのが現状です。しかしながら、皆さんの気力と体力、そして協力により、ほぼ自力で開催できております。
このような中、今年度、初の試みとして、巡回展の初日にギャラリートークを企画しました。展示指導においでいただいた渡邉良一先生には快く引き受けていただき、展示作品の説明のほか作画の苦労や色彩についての話をしていただきました。また、同時に開催した支部公募展に出品された方の中から2名が入会して下さったこともあり、良い巡回展になったと思っております。